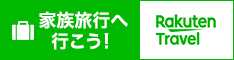ふづきです。
先日の「暑さ」の話から
程なくして「寒さ」を感じるのは、
温度よりもその「差」が大きい。
差と言うのは、
身長差や歳の差などの数字の上だけ
ではなく、
見た目と性格のギャップという
意味合いでも使われたりする。
その差が大きいと
感じるものも大きくなるようで、
その驚きは良いも悪いも
肌に心に響かせる。
海抜0mないし海底に湧く温泉から、
標高2410mのそれは、
どれもこれも
驚かされるものばかりで、
差があるようで似て非なるもの。
言葉ひとつ事ひとつ、
拾い上げ眺めて見ると
見てるようで見てなかったなと、
部屋の隅から面白さを見つける
今日というただの、
たった1日しかない時間(とき)を…
振り返り
<2021年 6月>
今回で立山アルペンの旅は最終章を迎える。
自分たち夫婦(ふづきとさつき)は、日本最高所(2410m)の温泉宿『みくりが池温泉』を目指すことが目的。嫁のさつきはダイビングで、式根島にある『海中温泉』に潜って行ったことがあるので、もしかしたら高低差日本一の温泉を達成したことになるかもしれないと、自分は勝手に想像してニヤけている。
前日に『金太郎温泉 カルナの館』にてETC割引を使ってお得に濃厚な乳白色の温泉へ入浴し、立山駅無料駐車場で朝一のケーブルカーへ乗るために車中泊をした。新緑の6月でありながら、朝晩は涼しさを感じる立山駅は標高475m。ここでの星空ですら澄んで見えたが、2000m超の空はどれほど近くに感じられるのだろうかと、期待に胸が高鳴る。
ケーブルカーと高原バスの乗り継ぎ、辿り着くその姿は若草色とは程遠く、空と同じ青と白のパレットに差色の緑。安心という言葉を掛けてくれたのは、季節通りの暖かな陽射し。まだ長い、出口の灯りが見え始めたトンネルのような冬を終えようとしている室堂の雪壁。標高2400mを越えるということはこういうことなのかと、そう言わんばかりにそびえ立つ『雪の大谷』はこの陽射しの中でも10mを誇示している。シーズンでは20mもの姿を魅せ付けられるとなると、脱帽以外の言葉が見当たらない。
ローストビーフ重で腹と心を満たし、目的地を通り越しての冒険の旅へ。空腹で独りだったら挫けてしまいそうな細く長い1本道。嫁のさつきとふたりなら、いつでもどこまでも。火山ガスが噴き出す地獄谷を横目に、(今は雪で覆われているが)それは赤く染められているという血の池。地表からは硫黄の結晶のようなものや、まるで魔王の城へと誘う屍のような木々に。靄を纏うその館の名は『雷鳥荘』。達成感と共に頂く源泉かけ流しの温泉は至福のひとときで、立山の地下水は見逃してはいけない純粋さ。
この上をゆく高さには、
どんな驚きが待ち受けているのか。
とてもワクワクさせる。
みくりが池温泉

前回の記事でも触れたが、ここだけ雪の気配がない違和感を覚える。温泉が湧いているからか、地獄谷との距離感のためか。6月だったということを思い出させるような、そんな感覚に陥る。『雲表の温泉』と書かれているが、雲の上という表現がこれほど似合う温泉はとても珍しい。

みくりが池温泉から程なくしてある、地獄谷展望台の様子。ここは雲の上…というより雲の中なのかもしれない。まるでラピュタのワンシーンのような、少し歩くだけでも雰囲気がガラッと変わるのが面白い。ここからは、火山ガスが断続的に噴出している地獄谷を一望することが出来る。だから『エンマ台』ということなのだろう。
詳細

名称 みくりが池温泉
所在地 富山県中新川郡立山町室堂平
TEL 076-463-1441
入浴 日帰り可(9:00~16:00)
料金 大人800円 小人600円
補足 室堂駅より徒歩15分程
(注)時期によっては雪道や吹雪くことあり最新の情報要確認
公式サイト
http://www.mikuri.com/
地図
※出典:Googleマップ
内観
エントランス

日本最高所の温泉であり秘湯でもある。
辺鄙な場所でありながら、登山家や温泉愛好家に大切にされてきたのだろうなと、自分たちのような半人前にも温かく迎えて頂けたことに感謝したい。
廊下と踊り場


客室のある2階へ上がるとビジネスホテルのような間取りの廊下が目に入る。嫁のさつきから聞いて驚いたことは、登山する方のいわゆる山小屋のような役割をしているようで、今回自分たちは個室を利用させて頂いたが、他の部屋は8人やら4人の相部屋(男女共用、女性専用)らしい。登山仲間で宿泊しているようで、時折楽しそうな話し声が廊下に漏れてくる。
1階から2階へ上がる途中の踊り場には、大量の本が綺麗に並べられている。個人的にはあまり興味をそそられるものはなかったが、そんな自分でも「山が好きなんだな」と思わせるタイトルばかりに、何故だか気持ちがほっこりした。
客室(個室)

客室の扉を開けて一目ですべてが把握できるくらい。究極のミニマリストになると、気持ちもスッキリするかもしれないと。意外とそれも良いかもしれないなと、気付かされた瞬間だった。
それとも、
「山がある。それだけで良い」と思うのか。

うろ覚えだが、テレビがないのは立山の山の景色を楽しんでいって欲しいことが理由だった気がした。何を目的にここに来たのか、を考えれば答えは始めから出ていて、泊まれる場所があるだけ有難いことで、普段の日常がどれだけ物で溢れ返っていたことか。便利さゆえに、見失っていたものばかりな毎日だったということを改めて思い知らされる。
食事
夕食

夕食は1階にある食堂にて。
あまり期待をしていなかった分、豪華な食事を頂けたことは覚えているが…。結局のところ、ビールがメインになってしまったのは致し方ないことで…笑。こんな辺鄙な場所で、何種類ものメニューと大好物のビールまで頂けるなんて、それだけで贅沢な気分になれるのはココならではなのかもしれない。
ちなみに、ビールの右側にあるのが富山県の郷土料理『さすの昆布じめ』。『さす』とは富山県の方言でカジキのことを呼ぶよう。ねっとりとした甘みのある食感で、これまたお酒に合う。


夕食とは別で注文したのが『白海老の天ぷら』。
嫁のさつきが富山に来たらどうしても食べたかった物のひとつ。おかずと言うよりはおつまみ。サクッとしながらも、白海老特有の甘さが後を引く旨さ。
それと、一人用の鍋でグツグツと煮込まれていたのは、まさかのアンコウ鍋。こんな山奥でアンコウに出逢えるとは…。
朝食

朝食は、これぞ朝食というメニュー。
朝から腹いっぱい頂けて大満足。温泉に何度も入ると、それだけで腹が空くということは、やはり入浴は意外と体力を必要とするのだろう。
温泉
洗面所と男女別内湯


1階の食堂の並びに洗面所があり、そこを抜けると男女別の内湯へと繋がる。洗面所には無料のドライヤーが設置されていて、親切に給水機まである。
ここまでの造りを見る限りでは、どんなお湯が、どのような雰囲気が待ち受けているのか、全く想像が出来ないところが更に興味をそそられる。
温泉成分表など


源泉名 みくりが池温泉
泉質 単純酸性泉(低張性・酸性・高温泉)
泉温 54.3℃
pH 2.18
補足① 源泉かけ流し(加水・加温・消毒なし)
補足② 男女別内湯(熱湯・ぬる湯)各1
脱衣所(男湯)


浴室の扉からは想像できない、木のぬくもりを感じさせるような柔らかさがある脱衣所。日帰り客には嬉しい、無料の鍵付きロッカーも用意されている。もちろん脱衣カゴも別に用意されていて、使い勝手の良さもある。疲れた身体を癒すときに、このような落ち着きさをを取り戻せる空間があると、特別何かをするわけではないけれど、何だかホッと出来たりするから不思議だ。

脱衣所にある、たったひとつの小窓。
それだけなのだけれど、妙に魅力を感じてしまう。ポツンとありながらも、目線を奪われてしまう存在感。窓の役目とはまた違う、そんな何かに引き込まれた、たった数秒を残したくなる。言葉では表現しきれない一枚。
内湯(男湯)

浴室の扉を開けてすぐ左手に、洗い場が備え付けてある。シャンプー等一式あるため、登山で急な日帰りでも安心。高所であるにも関わらず、たっぷり水とお湯が使えるのはありがたいこと。

浴室の扉を開けて正面にある、(大きさ的には広くはないけれど)まるで大きなスクリーンと舞台のよう。
窓一面には雪化粧した山々。うっとりさせる美貌の立山連峰と地獄谷が目に飛び込んで来る。目線を戻す前に、吸い込むそれには硫黄が纏う。あの地獄谷から源泉を引いているようで、目から鼻からここの空気を感じ取ることが出来る。


お湯の見た目は、秋田にある『鶴の湯温泉』や、福島の『あったか湯』に近いものを感じる。
www.fuzuki-satuki.com
www.fuzuki-satuki.com
けれど、
入ってみると似て非なるもので、硫黄の強さよりも酸性に傾く酸っぱさがあるものの、だからと言って梅干しのような顔をしかめる感じではなく、まろやかさに秀でているような。あの地獄谷から引いているとは感じさせないくらい、この6月の晴天の山々のように穏やかな気持ちにさせる。硫黄泉や酸性泉が苦手な方でも入れそうな。決して成分が薄いわけではない証拠として、湯上りは硫黄と酸性のダブル効果でつるスベ肌確定。

個人的には熱湯(45~6℃)が好み。地獄谷のモクモクした蒸気を眺めながら、ここに来たという証を身体中に感じる。ここでしか味わえない贅沢を…。

ぬる湯、熱湯ともに設置されている水の出るコック。朝一の熱湯は、湯もみされておらず確かに熱い…けれど、ありのままを掛け湯を(十分に頭に掛けて)して入るのも、これまた贅沢なひととき。
載せきれない写真たち
実際見る景色と写真とでは、見え方や感じ方が異なったりする。それもまた面白味があったりするが、ここにはそのほんの一部を残しておく。





朝と夜とで、同じものが違うものに見えたり感じたりするのも、ここでしか体感することのできないひとつの楽しみ方だろう。
まとめ

日本最高所(2410m)と聞いて、初めは登山でしか行けないような場所と思っていた。確かに登山で楽しまれている方々も多くおり、中部山岳国立公園でありマイカー禁止区間という守られた環境。自然に限りなく近い、ありのままの姿を目で肌で感じることが出来るのは、教科書では得ることの出来ない貴重な体験だろう。
今回は、ケーブルカーと高原バスを乗り継いで、少しばかり歩いて辿り着いた温泉宿だったが、それでも普段の旅とは違う空気感、特に『音』の特別感には嫁のさつきが何度も言及していた。
それが日常ではあり得ないことだという現実に。

普段どれほど音というものに支配されて生活してきたのか。静か、とは違う。無音、の方が近い。
好きな歌や曲を聞いてリラックスしてきたが、日常に疲れた時は、ここに来た方が余程良い。
目に映るそれらは、本当に存在するものなのかすら、そのときばかりはどうでもよく感じて、気付いた時にはふたりとも言葉を発せず。ただ、ただ、目の前を見て、時間すら止まっているかのように。
また来る必要がある。
標高と温泉もさながら、ここの素晴らしきはここにある全てかもしれないと。
もう一度、いや、二度でも三度でも、ここでしか味わうことの出来ない出逢いをしてみたいと思ってしまう。