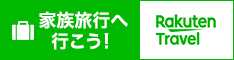ふづきです。
新たな地での冬にも
段々と慣れ始め、
普段通る道の
風景を景色として
”見てた”から”見てる”へ。
白という色は
キャンバスの上では
決して目立たなくとも、
この目には
眩いばかりに
感動をも映し出す。
自然の織り成す術を
似て非なる真似事は出来ても。
心に届くそれは
言葉なしで
確かに伝わり響く。
はじめに

<2021年10月~>
東京湾フェリーターミナルから四国徳島へ上陸し、
嫁のさつきと共にぷちキャンカーでめぐる夫婦旅。
船旅と車旅を合わせて9泊10日のロングラン♪♪
乗船日から数えて、この日は4日目の15時頃となります。
ー 初日は18時間の船旅からスタート ー
www.fuzuki-satuki.com
ー 2日目は徳島上陸、9日目に名物満喫の徳島で車中泊 ー
※徳島でまとめています。
www.fuzuki-satuki.com
ー 2日目は夕陽の待つ恋人の聖地へ ー
www.fuzuki-satuki.com
ー 2日目の〆は高知名物で晩酌、そして車中泊 ー
www.fuzuki-satuki.com
ー 3日目の朝は坂本龍馬と桂浜散策 ー
www.fuzuki-satuki.com
ー 3日目の昼は神秘的な仁淀ブルーと郷土料理 ー
www.fuzuki-satuki.com
ー 3日目の夜は珍しいカルスト高原で車中泊キャンプ ー
www.fuzuki-satuki.com
ー 4日目の朝昼は沈下橋とかつおたたき丼 ー
www.fuzuki-satuki.com
今回のメインは、
四国最南端の”足摺岬”と絶景穴場スポット”龍宮神社”。
予想を遥かに上回る事態に、
たった数十分の出来事が今でも忘れられずにいる事実。
正直、”言葉”を失いました。
足摺岬
足摺黒潮市場から足摺岬
※出典:Googleマップ
・名称 足摺(あしずり)岬
・所在地 高知県土佐清水市足摺岬
自分たち夫婦は、四万十川の文化的景観である”沈下橋”のひとつ『中古屋沈下橋』を訪れ、少しばかり高知という土地柄や歴史に触れたような気がしました。
そこからトイレ休憩を兼ねて立ち寄った『足摺黒潮市場』での昼食は、高知名物”かつおたたき”を丼ぶりで。しかも、食べ方は特製の出汁をかけて味わった後のご飯に、かつおフレークをふんだんにかけて満喫するというもの。お腹も心も大満足でした♪
そこから12.5km(16分)の距離を南下し、
四国最南端の『足摺岬』へ向かいました。
(四国という)島めぐりをすると、
その島の端っこに行きたくなりますよね!?笑
走り抜ける

高知県の”岬”は、以前に室戸岬へ足を運んだので、今回で2ヵ所目となります。
何やら有名人の後ろ姿が見えます。
この方はどちら様でしょうか?
ジョン万次郎


中浜万次郎と聞くといまいちパッとしませんが、
ジョン万次郎と聞くと「聞いたことがある」と思うのは自分だけでしょう。(歴史がとても苦手でスミマセン…苦笑)
詳しい内容は、上の写真を参照していただけると幸いです!
簡単に説明すると、
日本人として初めてアメリカへ渡り、鎖国から開国に掛けて陰で支え、明治文化の開花に著しく貢献した人物のようです。
自分の歴史上では、
父親が飼い犬に付けた名前が
『ジョン万次郎』
だったことで有名です…はい。
※実話です
周辺観光案内

今回は駆け足で巡ってしまったため、(本当は途中で引き返したという事実…。)これを見る限り中浜万次郎の像だけでなく、天狗の鼻や亀呼場など見どころは沢山ありそうですね!私事ですが…最近”釣り”を覚えたので、磯釣り場は何が釣れるのか気になります。
様子

出入口を入ってすぐの様子。
和と洋が混ざっている理由、きっとジョン万次郎の生涯を表現しているのかもしれません。不思議な感じはしますが、何だかこれはこれでバランスが取れていて、妙に良い感じですね♪


これぞ、断崖絶壁…。
感動よりも恐怖を覚えてしまうような、断崖絶壁感。
荒れ狂う波に数多に削られ、今に至ったのでしょう。ということは、これからも削られていくのでしょうか?そんな海で育まれた”かつお”は、とても逞しく旨味が凝縮されているに違いありません。
龍宮神社
足摺岬から龍宮神社
※出典:Googleマップ
・名称 龍宮神社
・所在地 高知県土佐清水市松尾
足早に足摺岬を後にし、次の目的地へ向かおうとしていた矢先。調べていると気になるスポットを発見しました。「何か端っこに神社があるけど、ここから夕陽が見えるかも!」と。この時の時刻は16時になろうとするところ。17時頃には陽が沈むので、これはチャンスだと思い車を走らせました。
足摺岬からは7.2km(12分)。
ちょうど良い距離と時間。これは運命ですね!!
入り口は突然

車を走らせていると、ナビの「目的地周辺です。お疲れさまでした」というお決まりの道半ばでのアナウンス終了。
平屋の建物と駐車場があるだけ。
車が1台と自転車が停まっていますが、人の姿が見えません。
どこ?
辺りを見渡すと、隅っこに石造りの鳥居がありました。

確かに『龍宮神社』のよう。
ここを入るの?
と思ってしまうような薄暗い森の中へ続く道。
もう一度辺りを見渡しても人の姿は確認できません。やはり、この先にいるのでしょう。現在時刻は16時15分。日の入りは17時15分予定。これは行くしかないですね!
光の届かない森

なぜ”光の届かない森”という表現をしたかと言いますと…
実際足を運ぶと分かるのですが、太陽が昇っているときはまだ道が分かるくらいの明るさ(それでも薄暗い)。それが陽が暮れ始めると…。もう道なのか獣道なのか、それすら識別できないくらいに真っ暗になります。足を運ぶなら、日中。遅くなるなら懐中電灯は必須ですが、遅い時間に来ると足を踏み外したり、イノシシに襲われる危険もあるので注意が必要です。
”絶景展望所↑”という看板があるのですが、明らかに狭い道。今回は龍宮神社を目指すため、看板に従って(写真では左。実際は直進方向)進むことにしました。

太陽の光は安心しますね。
ほとんど光がほとんど差込まないため、この場所のように光があるとホッとします。明るいって大事ですね!部屋に一日閉じ籠っていると気が滅入ってしまうのは、人と太陽の関係性にあるのかもしれません。
分岐点

大平監視台と龍宮神社への分岐道。
大平監視台…意味深なワードに興味を惹かれますが、日の入り時刻を考えるとここは先を急いだほうが良さそう。そう判断して、龍宮神社へと続くであろう分岐を右へ進むことにしました。

神社というものは、
こんな森の中の狭い道を抜けて行くものだったでしょうか?
奥へ進むごとに外の世界と乖離したような、音がなくなっていく感覚に陥ります。”神聖な”と言えばそうなのかもしれません。もし、嫁のさつきと一緒ではなく独りだったら…。間違いなくこの入り口すら潜っていないことと思います。
光が差し込む森


時は10月の末頃。
決して暖かくはないものの、そこまで寒くもない気候。けれど、日陰を歩いていると肌寒さを感じるくらいで、そこに陽が差し込むとそれだけで温かさを感じるのは、やはり太陽の力なのでしょう。これだけ草木が生い茂っているのは、ここがそれだけ陽当たりの良い場所なのだと教えてくれています。
森を抜けた先は
歩いた時間はものの数分。
10分?15分?体感的にはそのくらいに感じたような気がします。
薄暗い森の中をひたすら進み、
正直不安すら感じながら歩き続けました。
薄っすらとした光から、
目が眩むような白色に…。

ここはどこ?
眩い光と共に、
森の中からは想像もできない
まるで龍宮城のような海へと続く一本道が目の前に現れました。



一体自分たちはどこに来たのだろうか?
確か、平屋の建物のある駐車場の一角。その鳥居を潜り、日中でも薄暗い森の中を抜けて…。その先にこんな明るい、想像を遥かに超える景色に言葉を失いました。
この一本道はどこへ続いているのだろうと、本当に龍宮城にまで続いているのかもしれないと。本気で思わせてくれる空気に、夢の中のようなフワフワした感覚で音のしない岩場をふたり歩いていました。
振り返ると

気付けば、
こんなにも歩いていて。
どれだけ深い森を抜けてきたのだろうかと、
帰り道を考えずに来たことを後悔する暇すら与えず。
感動と茫然の狭間で目にしているこの景色は、
来る人の言葉を、心をも奪ってしまいそうで。

岩場に出来た窪みに、ただ水が溜まっただけなのに。
鏡よりも綺麗に映し出す水面は、
本当に自然が創り上げたものなのだろうかと疑ってしまうほど。
朱色の鳥居と海の神

海に向かって、
ただただ佇む朱色の鳥居。
説明書きなど何もない。
むしろいらないのかもしれません。
ここにあることが、
それこそが一番の意味であって理由なのだろうと。
わけもなく手を合わせる自分たちがいました。
そんな時、
一人の男性が声を掛けてきました。
徳島県からここまでサイクリングでよく足を運ぶそうですが、この景色を見てそう話して立ち去っていきました。また、陽が落ちると森の中は真っ暗になるので、暮れる前に帰った方が良い。と教えてくれました。

海の神様がどのような姿かは分からないけれど、もしかしたら人の姿ではなく岩にしがみ付いているような姿かたちをしているのかもしれません。自然と浮かび上がった形が、それのように見えるだけなのかもしれませんが、見る人の心持ちによって変わるものなのでしょう。勝手ながら、そう思っています。
まとめ

日本で初めてアメリカに渡って勉学したという”中浜万次郎”。
彼の待つ『足摺岬』は、幾年の歳月で浸食された断崖絶壁で形作られ、名前の由来は分からないけれど足を引き摺ってしまうほどの恐怖すら感じてしまいます。ただ、それが魅力と思ってしまうのは、人という生き物は良くも悪くも”酷”だなと。つくづく思います。
坂本龍馬といい、中浜万次郎といい、
今いる文化のみならず新しきを受け入れる柔軟さ、そして熱意と行動力。その源は一体どこから来るのでしょうか。あの荒波を毎日のように眺めていると、気付く何かがあったのかもしれません。
知る人ぞ知る穴場スポット『龍宮神社』。
海の男たちの豊漁と航海安全を祈願し建てられたと言われています。あの”浦島伝説”の龍宮とは関係はないそうですが、海へと続く1本道はそれを連想させてしまうくらい。
静寂な森を歩いていると、自然と気持ちは落ち着き、現実を冷静に考えてしまいます。その心持ちを一瞬にして奪い取る白色の眩さ。まるで乙姫様にでも出逢えたような、そんな驚きと興奮さを一気に高めてくれる浸食された岩々。足摺岬で見たそれとは違う、恐怖よりも感動。紛れもなく歩いていたはずなのに、フワフワと浮いていたような足取りは、もうすでに心がその空間に、景色に融け込み、混ざり込んでいたようで。
海の神様は、人の姿をしていなくとも、そのカタチというものは意味があるようでただの借り物だったり。その人に伝わってくるそれが全てで、それだけで十分だったりします。
地元の方の言うように
”ここの自然で創り上げられた景色の方が良い”
自分たちもそう感じました。
唯一無二の景色がここにはある。
…なんて、カッコいいことを言いたくなってしまいます。
ただの寄り道がこんなにも満足できる場所だったこと。
知らないだけでものすごく貴重で素晴らしいスポットが、きっとまだまだあるということ。
”気ままに自由にノープランで”
嫁のさつきと旅する、ひとつの理由です。